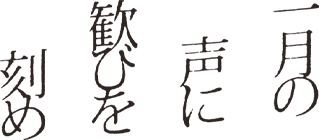※敬称略/順不同
3人の異なるキャラクターによる3つのエピソードの中に、存在、痛み、罪悪感、性暴力の生涯にわたる影響についてのドラマチックで美しい瞑想画が紡がれています。女性の鋭い視点で描かれている女性が中心の物語。長く魂に残る映画として、今回紹介したい作品です。
Sabrina BARACETTI(President,Udine Far East Film Festival)“In three episodes with different characters, it is a dramatic and beautiful meditation on existence, pain, guilt, the lifelong effects of sexual violence.
There is a centrality of women, according to a strong perspective of the female gaze! It's a film that stays in your soul for long time!”
サブリナ・バラチェッティ
(ウディネ映画祭ディレクター/最高責任者)
(ウディネ映画祭ディレクター/最高責任者)
作品は生まれた瞬間から、作者の手を離れ、
孤独な旅に立ってしまう。作品と作者の関係は、もうない。
三島有紀子は、自分の性を見つめながら、
やがて、自分の生に転換させんとする、誠実さがある。
秦早穂子 (映画評論家)
作家性とは
作り手の魂の叫びの輪郭。
劇場で受け取れてよかった。
斎藤工 (映画監督/俳優)
早朝、突き刺さる冷気、新雪をゆくと、その歩の度に足の裏は苦しみもがく叫びを聞いている。
そこから始まった映像作品は、数行の言葉たちの行間を見事な息遣いで囁き続ける。胸の内の何処かを触れられたまま観てしまう映画だった。
内藤裕敬 (劇作家)
昨日にさよなら言えなくて、明日にさよならを言う。
役者もみんなよかったが、カルーセルさんにはびっくりした。
あの、死んだ娘のことを独白するシーン、これができるのは他に誰もいない。
過去に引きずられ、さよならを言えないまま生きてきて、慟哭の涙。
そっかぁ......さよならをこれからは言えるんだ。
ほんの微かな希望、灯火が見える。
そうか、これは元気をくれる映画なんだ。
奥田瑛二 (俳優/映画監督)
三つのストーリー,三つのダイレクションで様々な人にボールを投げる三島監督。三つの根底に流れるのは,忘れたい記憶や消してしまいたい記録を超える事が出来た自分にいつか出逢えると願う気持ち。
佐藤浩市 (俳優)
言葉だけでは説明出来ないこと、
いくら時間を重ねても解決しないこと、
モヤモヤの中にいる人たちが、モヤモヤと共に日々を過ごしてる。
しんしんと音を立てずにいつの間にか積もる雪のように、
悲しみも、恐怖も人知れず静かに積み重ねて来たんだろうなと想像する。
その人だけが知る涙の種類、
その人だけが知ってる自問自答の時間、
それが本人達にとって不快で苦しくあったとしても、
「人」を感じた時に、私たちはやはり愛しいと感じてしまう。
それも人の性質なのかな。
自然の景色の中で自然に滲み出る
人物それぞれの生きてきた時間は、決して悲しみだけではなく、
温かいものも一緒に連れてきてくれたんだと、
雪景色の寒さに反して、
不思議と温かさと心地よさを感じた映画でした。
田中麗奈 (俳優)
罪の意識に押し潰されそうなったって
人は歯を食いしばってでも生きてく義務がある。
日本の都と島と湖という全く違う場所で描かれる物語に、いま生きている実感を与えてもらえた。
当人しか理解し得ない、美も、罪も、憎悪も、ぜんぶ魅せられた。そして背中をおしてくれた。
水川あさみ (俳優)
奇跡の映画。人間の小さな魂が巨大なものに立ち向かっている。涙が止まらない。負けずに、生きていかなきゃ。叫び出したいほど虚しい夜がこの先も僕たちを待っている。それでも誠実に、世界を見つめて、恋をして、歓びを刻んで、生きていきたい。この映画から受け取ったメッセージを、僕は忘れない。
藤原季節 (俳優)
ほんの一瞬の出来事でも、それが永遠になりうること。きっとそれは永遠より長い。
自分のままで生きることがどれだけ難しいか。
誰かに明かさなくても、たとえ理解されなくても、それを抱えるも抱えないも、他人に強いられるものではないと思うから。
生きる手触りを確認しながら、少しずつ重ねていきたい。
南沙良 (俳優)
震える気持ちに共鳴する自然達。
吹荒ぶ雪・猛り狂う波・鈍い炎が共に叫んでいた。
あらゆる光景が今も瞳に焼きついている。
三島有紀子監督の覚悟がスクリーンに漲り、思わず涙が溢れました。
篠原ともえ (デザイナー/アーティスト)
三島有紀子の一糸纏わぬ全裸を見せつけられた気がした。
踏み締めた土で泥まみれになろうとも突き進む、その気迫と覚悟が今後「ものづくり」をするどの分野の人たちへの刺激になる、そんな作品だったように思う。
伊藤亜由美
(株式会社クリエイティブオフィスキュー代表取締役/プロデューサー)
(株式会社クリエイティブオフィスキュー代表取締役/プロデューサー)
みんなどこまでも続くひとりぼっちを
一緒にいようとしてるのかもしれない
人は苦しい、苦しくて悲しい
悲しいから愛しい
二度と戻れないなら
どこへゆけばいい
必死で掴み取って立ち上がる人
それを呆然と見ているしかないのかな
産まれた時はまんまるなのに
あちこち穴が空いてしまう
どうにか埋めようと生きる
人は悲しいし、悲しいから愛しい
これは自分の人生じゃない
と思いながら自分の人生を生きなければならない
押し付けられたものを
こんな自分になにがわかるというのだろう
呆然と無力を生きるしか無いのかもしれない
この作品に対して自分の言葉を
自分のどの部分を開けばいいのか
混乱して見つからず
成す術なく過ぎてゆく
世界中のあらゆる苦しみ悲しみへ
どんな顔をして立っていればよいのだろう
世界中のあらゆる苦しみ悲しみへ
はじめの一歩はどう踏み出すのだろう
奇妙礼太郎 (ミュージシャン)
2時間あっという間でした。
本来愛の表現であり血を分けた命を生み出す行為なのに
なぜ暴力になるとこれほどまでに傷ついてしまうのか。
「汚れた」ってなんなの。
この国が性をタブー視して醸成された空気で女を物扱いするから出る言葉だ。
その空気もやっと少しずつだけど変わりつつある。
この映画は今観るべき映画だと思います。
カルーセル麻紀・哀川翔・前田敦子の
魂を絞り出した一月の声は深く深く刺さりました。
三島さんが過去と向き合うのは
どれほどの痛みだったかと思われます。
それをしっかり物語に昇華されてる。
素晴らしい作品を生み出してくださってありがとうございます!
ところで…
マンガ家志望のトトくん
すみません、私も彼と同じことしてました。
この顔色っぺー!と思って…
マンガ家の業ですね(ノ∀`)
ということで描きました


もんでんあきこ (漫画家)
僕の心にあるいつの間にか感じたくない、見ないようにと伏せて生活している孤独が『一月の声に歓びを刻め』には映し出されていました。
心からの叫べる声はいつでも痛いけど、愛から生まれるから希望にもなるんだと思う。
決して楽では無い映画だけど、三島監督 撮ってくれてありがとう。
落合宏理 (ファッションデザイナー)
静謐なのに烈しい映画だと思いました。
カルーセル麻紀さんの演技が凄まじく、雪の中、黙って水面を見つめる眼が、静かなのに鬼を呑んだようなまなざしで、
どんな人生を歩んだらあんな目になるのだと震えが走りました。
マキの丁寧な手料理と暮らしの下にひそむ消えない傷みと烈しさ、「傷み」について描かれた映画だと思いました。
痛覚の痛みは消えたり薄まったりしますが、それこそ傷痕のように消えない忘れられない傷みはあります。
それでも、抱えながら生きていくしかなくて、そういう人間に対する許しや愛を感じました。
雪の軋みや凍らない湖、海鳴りや太鼓、モノクロの街、それらが登場人物の傷ついた心の在り様を映していて、
あらためて映画の表現方法が好きだなと思いました。
千早茜 (小説家)
あれはある夏祭りの日だった。浴衣を着てひとり歩いていた幼いわたしの隣を通り過ぎようとした車が急に停車し、運転席の見知らぬ男に引き摺り込まれそうになった。とっさに手を振り払ってその場から逃げたわたしは、しばらくのあいだ恐怖で動けなかった。
この映画から聞こえてくる波の音がかつての記憶を召喚し、そして「もしもあのとき逃げることがかなわなかったとしたら?」という仮定を浮かび上がらせた。平凡そうな顔をした世界には、薄皮一枚で人生を奪い去る暴力がつねに潜在している。
映画の力を強く信じる作家が、映画を通して声を上げている――傷つけられてしまった「わたし」は、ほんのわずかな掛け違いで「あなた」だったのかもしれないと。どこか遠くの「わたし」の物語は、すぐそばにある「あなた」の物語でもあるのだと。
児玉美月 (映画文筆家)
映画作家の苛烈な自伝的要素を
人間の魂の形にした3章それぞれの主演者――
カルーセル麻紀さん、哀川翔さん、前田敦子さん。
俳優という身体の凄絶さに改めて圧倒される思いです。
殊に、並々ならぬ気迫で撮影に臨んだ前田敦子さんの演技に最大の敬意を。
前田さんの俳優人生を代表する一作になると思います。
荻野洋一 (映画評論家、番組等映像演出)
まさに動く芸術―――。
視覚から読み取る美しさ、聴覚から感じる温もり、
触覚ほど脳と直結しているという事実、
これを映画という手法で突きつけられた衝撃作。
どうあがいたって人間は出会った人に影響され
過去を背負いながら一生懸命、生きていくんだと
叫ぶような映画だった。
伊藤さとり (映画パーソナリティ)
罪の意識とともに生きざるをえなかった者たち。その途方もない収奪と喪失が、実験的映像によって雄大な自然と都市の風景に織り込まれる。これまでの三島映画では味わったことのない映像と音響、俳優の見事なアンサンブル。カルーセル麻紀の悲痛な叫びが、前田敦子の絶望と怒りの声が、きっと観る者の心の奥底まで響きわたるだろう。
大胆不敵にもこの映画の文体は三部構成を採りながら劇的に転調してゆく。八丈島は歴史的に罪を背負わされた人々をたくさん迎え入れてきた。特別な意味を担ってきたこの辺境の島が、洞爺湖・中島と大阪・堂島の間に、まるで両者の“れいこ”を歓待するかのように配置されている。この巧みな構成に思わずうならされた。
雪原の洞爺湖の空気感を丸ごと捉えた静謐なロングショット。八丈島で鳴り響く太鼓の音、荒れ狂う波飛沫、揺動するカメラ。堂島の魅惑的なロケーションを背景に繰り出される圧倒的な長回し——。この挑戦的な作品は、三島有紀子が紛れもなく新たな映画作家のステージへと到達したことを、われわれに体感させる。
北村匡平 (映画研究者/批評家)
「三島有紀子監督の渾身の作品、心に深く沁みました。
タイトルが謎めいているのも素晴らしい。何度でも、スクリーンで観たい作品」
北川れい子 (映画評論家)
いずれも難しい問題に真剣に取り組んでいて、その姿勢に感動する。
三島監督の丁寧さと、前田敦子さんの演技に圧倒されました。
田原総一朗 (ジャーナリスト)
誰もが、葬りたい過去を抱きしめ生きている。
そんな自分と手を繋ぎ、生き続けている。
幼い日の傷が見せる悪夢がある。
あなたにも、あった。
かたときも忘れないのは、
あるときひょいと思い出すのが嫌だからだ。
毎日傷と見つめ合うことで、痛みを逃がす術もある。
あなたは傷を元手に映画を撮る。
わたしは傷を元手に小説を書く。
演じるひとも、傷だらけだった。
撮ったひとも、血まみれだ。
観てしまったわたしは、
予想を超えた深手を負った。
生きてて、良かったと思う。
桜木 紫乃 (小説家)
自分を喪った「れいこ」は「零子」であり、「霊子」でもある。この映画との出会いによって、自分の中で息を潜め続けていた「れいこ」を発見したのは、私だけではないだろう。
無数の人々の中に、声なき「れいこ」が存在するのだとしたら、この映画で撮られた「れいこ」は「例子」、無数の「れいこ」の1人に過ぎないのかもしれない。
平仮名でつづられた「れいこ」の名は、観客に宛てられた手紙であり、観客に与えられた白紙の部分でもある。
マーサ・ナカムラ (詩人)
*追加コメントが到着!*
私は、私を愛す。罪をも愛する。
一月の声に歓びを刻め。
私の罪は、私にしか分からない。
外から見えぬように隠しているうちに、
罪は、私の身体の一部となっていた。
罪は醜い。罪は汚い。
私は罪を、自分自身からも隠そうとする。
自分のものではないと遠ざけようとする。
引き裂かれるような、その痛み。
罪は、明確な姿をもって目の前に現れることはない。
ただ痛みによって、その気配を感じるだけだ。
慟哭に近い声でつづられる、過去の自分に宛てた手紙。
余白もないほどに、紙は黒ずんでいく。
裏返すと、美しい白紙が現れる。
そこに私は、これからの自分に宛てる手紙を書く。
一月の声に歓びを刻め、と。
マーサ・ナカムラ (詩人)
人はみな孤島である。
跳ね橋をすべて上げる人もいれば、フェリーや高速道路でどんどん他の島とつながる人もいる。
しかしどんな島にも人は訪れる。
三島有紀子監督も私も映画に携わる仕事をしているが、高校時代、彼女とは奇しくもクラスメイトだった。
わいわい騒ぐ教室の中で、一人だけ大人の子がいるなと思っていたが、この映画を見て納得した。傷ついた子供は早く大人になる。
しかし同時に、彼女は明るかった。
押しつけられた闇と、それに対抗する生きる力。
つらい傷に向き合い、あのときどうすればよかったのか、自分はどうあるべきだったのかと何度も自問する。たとえ相手が悪くても。
傷に対するあがきは見る人への架け橋となり、心を打つ。ときに救いとなる。だからといって作者まで救われることはないが、人の意識の集合体のレベルを一つ押し上げていく。
前作「IMPERIAL大阪堂島出入橋」で編み出された実験的な手法は、本作でさらに進化しており、映画ファンを虜にするだろう。同時に従来の三島映画にあった水の質感や光の表現、人間の瑞々しい生活感や料理の魅力、人を見る目の温かさも健在である。
苦しみさえも少し楽しくなる映画である。
土橋章宏 (脚本家/小説家)
これを撮らないことには次に行けなかったんだろうなと切羽詰まったものを感じた。だからこそ「自主映画」での挑戦になったのだろう。ごつごつした手触りの中にある「生」と「性」が海で繋がっている。生きててくれてありがとう。
梶原阿貴 (脚本・俳優)
めちゃめちゃ面白かったです!
いますごいものを観ている!という思いが、胸の中で自然と膨らんでいくような映画でした!
(カルーセルさんが、イザベル・ユペールに見えました!)
大庭大作 (編集者)
生きていくって鬱陶しい。
老いていくことも
性も
自尊心も
ああ鬱陶しい。
そして怖くて不安…。
パチンと神さまが指をならせば
たちまち解決してくれるなんてことなく
“生きる”はグダグダ続いていくけども、
誰かに何かに依存しても救いはおきず。
でも
ある瞬間に何かの閃きのように
自分を救う歓びは
自分の中から湧き上がってくるんだと、
最後のあっちゃんの表情を見ながら
明るい気持ちになりました。
谷崎彩 (スタイリスト)
一年に制作される日本映画はおよそ600本と聞く。その内の半数以上が自主制作映画。私もいくつかの映画を自主制作したが、完成から公開までの道のりは決して平坦ではなかった。しかし誕生したばかりの作品を観た時の感激は、それまでの人生で経験したことのない喜びだった。
いわゆる商業映画の監督としてデビューした三島有紀子監督は長編10本目となる監督作を自主映画として製作・監督した。相当の覚悟があったことは想像に難くない。製作費も自分たちで集めたという。何が三島監督をつき動かしたのか。その答えはもちろん映画の中にある。
火傷しそうなほど熱い三島有紀子の魂が胸を貫く。どこへ向かって行くのか。もう怖れるものはない。天を翔けろ。
映画作家三島有紀子が誕生した。
菅原和博
(函館シネマアイリス / 佐藤泰志シリーズプロデューサー)
(函館シネマアイリス / 佐藤泰志シリーズプロデューサー)
とても息苦しかったです。
どこまでも続く美しい自然の中で、モノクロの都市の喧騒の中で、たった一人で おぞましい記憶と行き場のない憎しみを抱える彼らと共に、私自身息が詰まって とても苦しかったです。
違う時代に、違う場所で、違う状況で、同じ思いをしてきた人がたくさんいると思います。自分もその一人です。
しかし死にきれず、結局生きることを続けなければいけない事実に苦しみながら 日々をやり過ごすと、いつしか行き場のないその傷を抱えながら生きていくしかないんだな...と諦めなのか、前向きなのか...そんな風に思えるようになりました。
はじめに拝見した三島監督の「傷とともにのうのうと生きてやろう。」という言 葉に深く共感しましたが、鑑賞後改めてそれを実感しました。
今苦しみの最中にいる人たちにとって『お前は、美しい。』という言葉はどんな言葉よりも支えになるのではないかなと思います。
この作品と出逢わせ ていただきありがとうございました。
自分にとっても深く寄り添ってもらえるような作品になりました。
雪下まゆ (作家)
罪を抱えた人々は、いつか赦されるその日まで、
その罪を何度も見つめ、反芻し、血を流す。
傷を抱えた人々は、いつか赦せるその日まで、
その傷を何度も見つめ、反芻し、涙を流す。
湖畔でのマキの慟哭と、
れいこの歌声のリフレインに、
この作品は“人間讃歌”なのだと感じた。
エンドロールが終わっても、
暫く席を立てなかった。
ドリアン・ロロブリジーダ
(ドラァグクイーン)
(ドラァグクイーン)
水は どこにでも流れているが
その水が ほんとうに
真実に流れることは あまりない
私たちは ほんとうは
かっては水であり 水として流れ
水として如来したものたちであった
山尾三省 の詩篇『水が流れている』が思い出された。
洞爺湖のほとりで叫ぶマキ。八丈島の港で叫ぶ誠と海。そして淀川の河岸で声にはならない声で叫ぶれいこ。
彼らは水に向かって、過去の自分に向かって、叫び続ける。語り直し続ける。
いつしか彼らは水そのものになるだろう。
時間や空間を超えた悲痛な星々にもなるだろう。
夜空に瞬く無名の星々は、星座のような関係が立ち上がる。
その星々は語り継がれることでいつしか救済され、地上の我々の傷ついた心をも治癒してくれるに違いない。
ヴィヴィアン佐藤
(美術家・ドラァグクイーン)
(美術家・ドラァグクイーン)
「表現とは吠えること」と、誰かが言った。
ふんわりとした物語を紡ぎ出してきた三島有紀子が、今までの語り口を捨てて吠えた。
この映画は、三島有紀子の肉声。
映画監督として、新たな地平を獲得した叫びだ!
傑作である。
加藤正人 (脚本家)
三島有紀子監督の最新作。
自身の体験を込めたという物語で、熱意が伝わってくる力作。
第一章の終盤で台詞が少なくなり、海に沈んでいくかのような演出が印象的。
カルーセル麻紀の存在感にも圧倒される。
悲しみも苦しみも、いつか変化していくことを願わずにいられない。
池辺麻子 (映画ライター)
「誰かや社会を断罪する」という外に向かう怒りとは真逆の、内に向かう怒りを感じた。
決して自らに非があったのか、と自己を責めるということとは違う、自分自身を赦せない憤りだ。
静かな落ち着いた画面を見ながら、僕も内省的な思いに耽る時間を持つことができた。
それは三島さんの「個」の強い思いこそが可能にしたのだと思う。
大槻貴宏 (ポレポレ東中野代表)
予備知識を何も入れず『1月の声に歓びを刻め』を見ると、三つの話の関連性を考え、「れいこ」の名前だけが二つに共通するが、すると「八丈島」で生まれてくる子が「れいこ」になるのという意味なのだろうか?と思ったりしながら監督インタビューを読み、「堂島」は良く分かった。事前に読んでいると、見た直後の感想は大きく変わると思う。『息子の部屋』も知らなかったので配信で見たら、全体が掴めた。コメントを頼まれなければ『息子の部屋』は見なかったかも知れないが、見て感動して印象が強いので、そこから考えることになる。なるほどモレッティ君は、れいこのカウンセラーだったのか、そして「中島」は失くした子供に対する父親の後悔を癒すため、美しい風景と食事を更に美しく撮る必要があったのか、と解釈するが、やはり「八丈島」の本当の意味が分からない、「これはひとつの話だ」とされているから。前後が子供を失くすことをモチーフとしているので、生まれる子供を中に持ってきて、最後のれいこはその希望で自殺を思いとどまって心で歌う、と解釈して良いのか。
こういう者からのコメントで良いなら、宣伝的には三島監督の想いを全面的に出してゆく必要があると思う。
言えるのは「研ぎ澄まされた映像と演出の力強さで、その世界へ誘われ、登場人物たちの傷をヒリヒリと感じながら、そのなかで癒され、明日への活力が生まれてくるラストへ至る前田敦子の心の歌声が響く」ということであろう。
予備知識なくとも、これが言えるような作りが娯楽で、説明をしないセンスを磨くのが芸術なのか、説明の技術不足の問題なのか、こちらの不勉強なのか衰退なのか、いろいろと刺激的な作品である。
金子修介 (映画監督)
雪には”雪ぐ”という、静かで確かな力がある。
しかし、さいはてに降る一月の雪から始まるこの物語では、純白の雪は、新しくなって穢れを持たないものを表しはしなかった。むしろ下に埋もれる過去のよどみを、吹雪いてあからさまにして吹きすさぶ。疑いを知らない幼い時に負わされた心の傷が、決して雪がれることなく脈打っているからだ。
人知れず噴き出す血潮は、いつまで耐えてごまかしたなら”歓び”に変わるのか。
見終わった後、心の疼きが響いて痛くて、
ただ歩き続けなければどこにも帰れない気がした。
玉岡かおる (小説家)
三島有紀子監督が幼いころに受けたトラウマを、死を意識しながら現在まで背負い続け、自身と向き合い作った渾身の作品。
鋭いナイフで切り取ったような氷点下を感じさせる美しい映像、大阪の猥雑なネオン街がモノクロ映像で綴られ、三島監督が心の奥底に仕舞い込んできた記憶に勇気をもって向き会う姿が画面の背後から浮かび上がる。
掛尾良夫
(田辺・弁慶映画祭プログラミング・ディレクター)
(田辺・弁慶映画祭プログラミング・ディレクター)
誰も無関係ではいられない。この映画の中では、どんな人でも自分を見つけられる。光の強さや色味によって見えるものが違うだろう。私の中のいろいろなところにスクリーンから発せられる光が当たって、何かが動き出した。見終わった後は、もう、元の自分ではいられない。
及川史歩 (アーユルヴェーダ医)
魂の一作!
語弊がある言い方かもしれませんが…
おもしろかったです。なんか楽しんじゃいました。
そういう見方が良いのかわかりませんが、大きく前進するエネルギーを感じました。
観終わって、テーマやモチーフのことよりも、タバコ吸いたくなったり、お腹減ったり、お酒が飲みたくなる。そういう肉感的な邦画が減ってきてる(多分に好みによるのですが)なかで、嬉しい映画でした。
吉村知己 (プロデューサー)
三島有紀子監督の幼児期の体験を映画化したと聞いてかまえて映画を観始めた。観るにつれて、この映画は女性にも男性にも等しく語りかけているんだと沁みこんできた。洞爺湖と八丈島の水面。八丈島と大阪湾を結ぶ連絡船。ひとつひとつのエピソードが次のエピソードに繋がり幼児の記憶が今日の生活に結びついていく。性差や世代を問わない、多くのひとにひらかれた映画だと思う。
北條誠人 (ユーロスペース)
消えることのない傷に、ふたたび向き合い、
傷つきながらも、冷徹な視点で描いたこの映画に、
監督という表現者の真髄を見た。
そして、その映画に癒されている自分を知る
吉澤周子 (シネスイッチ銀座)
「自分語りはみっともない」なんて、語られたら都合が悪い人たちが私たちの口を封じるために使った詭弁なのだから、取り乱してまとまらなくても自分なりの語り方で想いを吐き出すのだ。それが直ちに治癒しない傷だったとしても。人から刻まれた傷を抱えながら、それでも他者と関わり合うよすがを見いだす本作が誰かにとっての光になることを願う。
奥浜レイラ (映画・音楽パーソナリティ)
私が常日頃想うこと。心でもいい、躯でもいい、じぶんの欠損を覆い隠すことも、じぶんの奥底を観て観ぬふりをすることも、逃げ場を求める監督にとっては、ありうること。が、いま、三島有紀子は、壊れるかもしれないことを畏れず、自身の背後にある暗がりを振り返り、そこからあらたに道を築こうと、この作品に臨んだ。劇中にあるまっすぐな科白は、あまりにまっすぐだから、なにもかもが三島有紀子で、それが、僕には、嬉しかった。こういうひとりぼっちの視座から、日本映画は、やり直してゆくべきだ、と、強く想った。みなさん、心がざわつくこと間違いなし、是非観てください!
阪本順治 (映画監督)
より大胆さと繊細さを加えた三島有紀子文学。カルーセル麻紀のパフォーマンスに圧倒されてしまった。デウス・エクス・マキナとは機械仕掛けの神の意だが、奇しくもカルーセルとは機械仕掛けの馬だし、マキナならぬ麻紀だし、偶然にしては彼女の演じる“父”は映画を支配して余りある存在感だった。
そこに描かれるは日本という機械仕掛けの島国の日本人という民族のささやかなる標本物語。それが切なくも愛しい。愛おしい。
岩井俊二 (映画監督)
残された人々の物語が折り重なったことで、より大きなものが生まれているように思えた。
雪を踏みしめ、歩く音。
太古からの歴史を孕んだような、太鼓の音。
そして、何より過去を語る、肉声。
個と個が繋がり大きな物語と結実する、映画の理想がここにある気がした。
瀬々敬久 (映画監督)
三島監督の決意と覚悟に見事に共鳴したキャスト・スタッフの力がスクリーンに漲っていた。それにしても、映画を見ながらこんなにも胸が苦しくなったのはいつ以来だろうか。かさぶたを無理やりに剥がして、傷口からもう一度流れ出た血をじっくり見続けるような作品なのだと強く感じた。この鈍い痛みを伴う傷と血の鮮やかさから決して目を背けてはならない。
菊地健雄 (映画監督)
圧倒された
映像に
俳優の演技に
三島監督の叫びに
何が起こるか全く予想がつかない
すごい映画
いや、映画ですら無かったのかもしれない
映画を超えた何かだった。
佐藤佐吉 (脚本家・映画監督)
あるひとの背負う過去について映し出そうとするとき、「何があったのか、そしてこれまでをどのようにして生きてきたのか」という現時点からの時間の巻き戻しによって語られる作品は多い。
本作もそれぞれ過去と葛藤する肉体が画面に放り出され始まりを迎えるが、この映画は傷を負った者たちに対して「今を、そしてこれからをどのようにして生きるのか」という前進について徹底して描かれていた。
だからこそ、この映画には画で語る回想は存在しない。
代わりに彼らから発せられる声でそれぞれの過去は再現される。私は、今を生きる肉体を目の当たりにしながら同時に声によって彼らの記憶を見た。
その二つの時間軸が映っているからこそ迫ってくる切実さがありました。
『一月の声に歓びを刻め』。彼らの傷はこれからもきっと癒やされることはないけれど、その呟きと独白、そして叫び声は画面の先にいる誰かを救ってくれるかもしれない、そんな思いでこの映画を見つめました。
工藤梨穂
(映画監督 『裸足で鳴らしてみせろ』)
(映画監督 『裸足で鳴らしてみせろ』)
その人にとっての苦しい出来事は、乗り越えるとか受けとめるとかそんな簡単な言葉で表現できるものではなく、起きてしまったことは、どうやっても消すことができないのだと思い知らされました。痛みとは何か──。映画のなかの見知らぬ人の痛みを通して、痛みの所在をいまも探しつづけています。痛みを完全に取り除く方法はないのだと思います。それでも、重りの塊を10持っていたとしたら、そのうちのいくつかを代わりに持ってくれるような、そんな優しさと力強さがこの映画にはありました。映画を観終わった後、あんなにも作品を、作り手を、ぎゅうっと抱きしめたいと思ったことはないかもしれません。抱きしめたくなるほど抱きしめてくれてありがとう、と伝えたい。
新谷里映 (ライター)
5分14秒。
暗転でサウンドが聞こえ始め、夜明けの海辺を見ているのかと思えば、いつの間にか客席の私が運動性と時間性という両方の翼で飛んできた、その美しき致命的なイメージの襲撃に息も大きくできないほど没頭してしまうのにかかった時間。
『一月の声に歓びを刻め』をフランスの知人に見せたかった。「映画を見ること」は単なる視覚行為ではなく、現実社会に対する問題提起で観客を思惟の領域に導き、その過程で理性とは異なる不慣れな感性の力を発見する「哲学的思考(pensées philosophiques)」の一環というジルㆍドゥルーズの定義を生得的に理解している稀有の傑作だと断言できるから。
しかし、推薦を先送りする。日本の観客は自ら克服すべき最大の相手が自分だという、孤独で美しい真理を痛感し、時には苦難に点綴される美学の旅を続けている三島有紀子の輝く一作を真っ先に鑑賞する資格があるのだ。
洪相鉉 (映画評論家)
不条理なことが起きたとき、人は、これを消化するために、その原因・理由を求めてしまうものだと思う。裁判で真実を明らかにしたいという思いも、そんな感情を基礎にしていることが多い。不条理に接した方々の中には、裁判が生きる大きな目的となる方もいる。
しかし、糾弾すべき相手が見当たらない場合、ましてや、不条理な事実について声をあげることとすらできないときには、すべて自分の中に抱えるしかない。
司法制度は、声を上げる人を前提にしており、また、人の感情に寄り添うことを主目的にするものとは言い難い。本作の登場人物を前にすると、その限界を鋭く突きつけられる。他方で、その不条理を抱え、生きる人に光を差せるのも、苦しむ人にその葛藤を吐露する場を提供できる人であるのだろうと気づかされる。
三島監督が、長く心に抱えてきた光と闇を見つめ続け、「罪悪感」の中で生き続けてきた人々こそが抱える感情を、俳優陣を通じて鮮烈に切り取り、ぶつけてくる作品である。
早川 皓太郎 (弁護士)
監督自らの体験を描いた真摯な映画であり『この体験を映画にして世に出す』という熱い思いが痛いほど伝わる
最初のエピソードの静謐さに作風にヨーロッパ映画志向のある三島監督ならではの映画を観ている体験を実感させてくれることに加えて、カルーセル麻紀さんの生き方と重なる役が静謐さに凄みを与えて圧巻である
今作を世に出した三島監督の人生への果敢な立ち向かい方から、こちらが刺激とインスピレーションを受けたように多くの方々も目を見開かれる体験をすることになるだろう
今作を完成させて公開していただいた三島監督に多謝しかないです
わたなべりんたろう (監督、ライター)
三つの島で繰り広げられる物語が引き寄せたのは、三島有紀子監督の想いと前 田敦子の身体性がシンクロした映画の奇跡。
大阪の片隅であふれ出す“れいこ”の魂の慟哭。
その切実さに、心揺さぶられずにいられなかった。
井上健一 (映画ライター)
生き延びる。生き残ってしまった以上は生きていく。
そして命ある限りは、生き抜いて欲しい。
罪と贖罪の物語が展開していく中で、三島有紀子監督のそんな叫びが聞こえてきた。
松崎まこと (映画活動家/放送作家)
人はそれぞれの事情を抱えながら生きている。だが、平穏であるために平静を装ってしまうもの。赤の他人が事情を察することは困難であるからこそ、三島有紀子監督は見えない<傷>を持った人々に対する共鳴を呼びかけ続けているのだろう。
松崎健夫 (映画評論家)
これほど女性の痛みが鮮烈に映しだされた作品をみたことがない。監督の勇気に敬礼。
小川深彩 (学生、映画監督)
刻まれた声に胸を抉られた。
どこまでも届いていきそうな叫びが世界を飛び越えて迫ってくる。
傷はやがて再生を呼び、その姿はこんなにも、涙が出るほど美しいものなのだと、
三島有紀子監督は示してくれた。
品田誠 (俳優、映画監督)
大自然や街並みを役やストーリーに巧みに惑わせて、人間の中にある、葛藤やトラウマを、独創的な演出で大胆にまた繊細に描き切る三島有紀子監督の作品に、強く心を打たれました。
白磯大知 (「石とシャーデンフロイデ」監督、俳優)
あのとき深すぎる海の底で届かないと知りながら発していた「声」は、
同じように遠く離れた時間・場所に閉じ込められた誰かと
どこかでつながっていたんだと知る。
ぽつんと残されたものを拾ってみたら、それは希望だった。
田中さくら (「夢見るペトロ/いつもうしろに」監督)
彼女たちの深海のような、光の届かない強い目が忘れられない。
深い海に潜り込んで、息苦しさを知りながら海底のようなこの世界を歩き回り、彼女たちへの圧倒的な計り知れない距離という真実をまざまざと体感してしまう。
秋葉美希 (「ラストホール」監督・俳優)
引き算を重ねた静かな熱量を浴びて、"自主映画"の強さと価値を再認識しました。
柴野太朗 (映画監督)
私は三島有紀子監督のもとで何度か助監督として就いたことがある。
ある人は三島監督を「孤高の人」だと言った。
私の目にも、監督は苦しそうになにかと闘っているように見えた。
映画の中の彼女たちもそれぞれの苦悩に直面し葛藤しながらも、もがき続ける。
胸を締め付けられるも、彼女たちの目の奥に光る強い意志から目が離せない。
立ち止まることなく動き続け、生きるために叫び続ける。
自らを否定したくなるほどの穢れを纏っていたとしても、
私はその人だけが持つ生きる力強さ、美しさに心を打たれた。
そうだ、三島監督も揺るぎない強固な眼差しで映画を作っていた。
大黒友也 (「ゴミ屑と花」監督、助監督)
奥めいた場所ほど、踏みしめた雪も、摘んだ草も、数日経つと元の姿に戻る。
覆い被せるしかなかったほどの感情に向き合う時、しつこいほどその心の場所に赴かなければいけないのかもしれない。
音のせぬ叫びと回復の、歪なその過程を、美しく悠然と見守ってくれるような作品だと感じました。
心を鎮める様に何度も何度もこの映画を見たくなる予感がしています。
大西諒 (「はこぶね」監督)
それぞれの土地の登場人物達が性に向き合う様をどう捉えたらよいのか、
その答えをこの映画自身が探し求めているようだった。
そうして一つ一つ確かめるように描かれた先にみつけた生への希望を救いと呼びたい。
西川達郎 (映画監督・脚本家)
三島有紀子監督と私は同い年で、テレビ局に勤務したのちに独立したという点も一緒。30代からの知人でもあり、勝手にシンパシーを抱いていた。だから『東京組曲2020』の舞台挨拶に招いてもらったときに「お互いこの世界でよく生き残ってきましたね」と軽口を叩いたが、撤回する。私は見誤っていた。三島さんは映画の世界で「生き残らざるを得なかった」のだ。そして自主製作でスタートした本作『一月の声に歓びを刻め』によって、これまでと違う次元の作家になった。尊敬、しかない。
大島 新 (ドキュメンタリー監督)